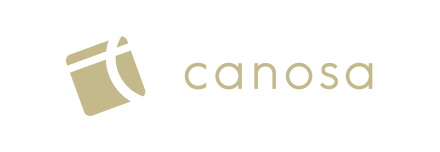canosa story Vol. 18 出羽の雪のかげり 新庄東山焼
【canosa story Vol. 18】 第18回目
今回は山形県の焼き物のお話です。(吉良のレポート)
新庄東山焼は、山形県新庄市に伝わる歴史ある窯元で、その起源は江戸時代後期の天保12年(1841年)に遡ります。初代の涌井弥兵衛が開窯し、新庄藩の御用窯としての役割を担いました。涌井弥兵衛は最初、瓦師として藩の瓦製造に従事していましたが、余暇に始めた器づくりが評判を呼び、陶磁器の製造を本業にしました。彼は越後(現在の新潟県)出身で、陶磁器作りの修行のため各地を訪れましたが、東山の良質な陶土に魅力を感じ、この地に定住しました。
新庄東山焼は、代々「弥瓶(やへい)」という名前を継承し、弥瓶窯(やへいがま)とも呼ばれるようになりました。現在では六代目まで、その技術と伝統が受け継がれています。初代から続く家訓「日常生活の中で誰もが親しんで使える陶磁器を作る」という理念は、現在の七代目にも大切にされています。
新庄東山焼の最大の特徴は、澄んだ青みの「新庄なまこ釉」で、これを「出羽の雪のかげり」と称しています。この美しい青色は、釉薬のかかり具合や窯の位置によって発色が異なり、器ごとに独特の濃淡が生まれます。他にも、そば釉、白釉、みどり釉、油滴天目(ゆてきてんもく)など、伝統的な釉薬と新しい技法を駆使した作品が多くあります。
新庄東山焼は、豊富な陶土を使い、全国的に少なくなっている「登窯」で焼成されます。この方法によって、素朴で味わい深い風合いが生まれます。東山地域は厚い粘土層に覆われており、ここで採取された陶土は焼き締まりやすく、丈夫で割れにくい特徴があります。そのため、使い込むほどに風合いが増し、長く愛用できる陶器として親しまれています。
また、民藝運動の祖である柳宗悦がこの窯を訪れ、独特の土鍋を「日本中のもので最も美しい」と称賛したこともあります。この評価は、新庄東山焼の美的価値と技術の高さを物語っています。
現在、新庄東山焼は伝統を守りつつも時代のニーズに応じた作陶が行われています。七代目の大介氏は、苔玉ポットや陶器水槽などの新しい作品を生み出し、人気を集めています。また、陶芸教室や出張陶芸教室を通じて地域とのつながりを大切にし、焼き物の魅力を広める活動にも力を入れています。さらに、環境問題に配慮した水質浄化用のレンガなどの研究・製作にも取り組んでおり、地域社会への貢献にも積極的です。
新庄市は、自然と歴史が調和した穏やかで落ち着いた美しい場所であり、canosaが好きな街の一つです。新庄東山焼は、170年以上の歴史を誇りながら、伝統を大切にしつつも常に新しい挑戦を続けています。その伝統と革新の融合は、多くの人々に愛され、今後もその魅力を発信し続けることでしょう。canosaでも人気のある陶器として、常時販売を行っていきます。
新庄東山焼の商品ページはこちら ⇒ 新庄東山焼