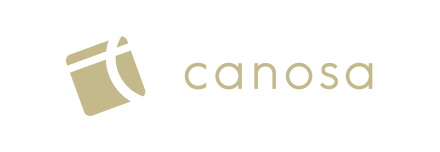canosa story Vol. 20 薩摩に根を張る線と色彩のうつわ
【canosa story Vol. 20】 第20回目
今回は鹿児島の焼き物について。(吉良のレポート)
鹿児島空港近くの姶良市にある宋艸窯(そうそうがま)を訪れました。ここでは、鎬(しのぎ)だけで陰陽を表現し、色彩豊かでありながら華美ではなく、家庭でも使いやすいシンプルなうつわが作られています。
宋艸窯は、1967年に竹之内彬裕氏によって開窯され、現在は二代目の竹之内琢氏とともに作陶を続けられています。彬裕氏は鹿児島市出身で、鹿児島市の工芸研究所などで陶芸を学んだ後、姶良市にて宋艸窯を開窯しました。
「宋艸窯」という窯名は、陶磁器が盛んだった宋(現在の中国)時代に由来し、草の旧字体「艸」を組み合わせたものです。この名前には、草のように根を張り、広がっていこうという思いが込められています。
工房併設のギャラリーで作品を選んでいる際、琢さんと奥様の眞弓さんからお話を伺いました。ギャラリーには、親子二代が手がけた器が並んでおり、その色合いや形、技法は驚くほど多彩です。琢さんは「父は基本だけ教えてくれて、あとは自分がやりたいようにやれ、という感じでした。だから、お互いが好きなものを、好きなように作っています。お互いに干渉せず、自由なものづくりを大切にしています」と語ります。
二代目の竹之内琢さんが陶芸を始めたのは30代初めのことです。幼い頃からもの作りが好きだったものの、陶芸には特に興味を持っていなかった琢さんは、金沢美術工芸大学で鋳金を専攻し、卒業後は京都で彫刻家の助手を務めていました。しかし、ある展覧会で出会った川喜田半泥子の茶陶に強く感銘を受け、陶芸の世界に引き寄せられることになります。これを機に実家に戻り、彬裕さんに師事し、陶芸の道を歩み始めました。
奥様も琢さんと同じ大学のご出身で、鹿児島の風物をモチーフにした箸置きや小物を作陶しつつ、こぎん刺しも手がけています。そのこぎん刺しは、愛らしさと素朴さが感じられ、非常に魅力的です。
薩摩の土は桜島の火山灰を多く含んでおり、陶土としては最適ではありません。しかし、試行錯誤の末、宋艸窯では信楽白土と天草赤土をブレンドした土を使用することで、オーブンの熱にも耐えうるうつわを作っています。天草は陶石の産地として有名ですが、ある日訪れた親戚の家で、細かい粒子の陶器用土を見つけたことが、素材選びの決め手となったそうです。
canosaでは、二代目琢さんの作品を取り扱います。
「陶造りは推敲の旅です。一字一行詩まで推敲は続きます。」と言う言葉からも分かるように、ものづくりに真摯に取り組む琢さんの姿勢が、そのまま作品に投影されており、どれも凛とした力強さを感じます。
深みのある瑠璃(濃紺)、どんな料理にも映える織部(緑)、鎬の凹凸が美しい粉引(白)を中心に、優しい梅色のマット赤やわら白、マット茶をセレクトしました。
宋艸窯から数分歩くと、錦江湾の奥に広がる穏やかな海岸にたどり着きます。姶良市には300年以上の歴史を誇る龍門司焼もありますが、宋艸窯は歴史や伝統に縛られることなく、自由な創造性の中で、薩摩の地に根を深く広げていくことでしょう。薩摩と琉球は古くから深い関係にあります。canosaでも、薩摩のみならず九州の焼き物を広く紹介していきます。
宋艸窯の商品ページはこちら ⇒ 宋艸窯