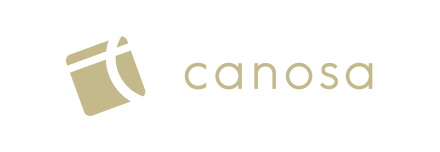canosa story Vol. 21 「沖縄再生の鏡」 琉球ガラスの神髄
【canosa story Vol. 21】 第21回目
今回は沖縄の伝統工芸である琉球ガラスについて(吉良のレポート)
琉球ガラスとは、沖縄県内で製造される吹きガラス工芸品の総称であり、主に「宙吹き」という手作業による成形技法を用いて製作されます。色鮮やかで温かみのある風合い、そして再生ガラスを活用した独特の質感や気泡を特徴としています。現在では、実用品としての器やグラスにとどまらず、美術品としても評価されており、2008年には沖縄県の伝統工芸品に指定されています。
琉球ガラスの歴史は、19世紀末から20世紀初頭にかけて始まりました。当初は主に日用品としてのガラス製品が作られており、その製造技術は本土から導入された西洋式のガラス製造法に基づいています。第二次世界大戦後、沖縄は米軍統治下に置かれ、資源や物資が著しく不足する中、米兵の利用したコーラなどの空瓶などを再利用したガラス製品が生み出されるようになりました。これが現在の琉球ガラスに見られる、再生ガラスならではの独特な色合いや気泡、ゆらぎや厚みといった特徴を生み出される起源となっています。1970年代以降、観光産業の発展に伴い、琉球ガラスは土産品や贈答品としての需要が高まりました。それにより、単なる日用品から芸術性を備えた工芸品としての地位が確立されていきました。
琉球ガラスの製造において中核となる技法は「宙吹き」です。これは、溶けたガラスを鉄竿の先に巻き取り、職人が口で息を吹き込んで形を作り上げる手法で、熟練した技術と感覚が求められます。加えて、色ガラスの調合、ガラスの厚みの調整、気泡のコントロール、冷却、研磨といった工程もすべて手作業で行われており、それぞれの工程に高い職人技が求められます。特に、再生ガラスを素材とする場合には、不純物の処理や気泡の調整が重要となり、これらが琉球ガラス特有の個性ある表情を生み出しています。沖縄の自然、特に青い海や鮮やかな日差しを思わせる色彩も、長年培われた経験と創造性の賜物なのです。
現在、琉球ガラスは沖縄県内の多くの工房で生産されており、観光客向けの体験工房も盛んに運営されています。地元産業のひとつとして認知されており、工芸品としての価値も年々高まっています。しかし一方で、後継者の確保、原材料の価格上昇、観光業の影響を受けやすい経済構造など、いくつかの課題も顕在化しています。また、「琉球ガラス」と謳われた安価な海外製品の輸入も拡大しており、それらと一線を画しつつも伝統技術を維持しながら現代の市場ニーズに応える柔軟性も求められています。
琉球ガラスの今後においては、伝統技術の継承と同時に、新しい価値の創出が必要不可欠です。若手の作家たちは、現代的な感性を取り入れたデザインやアート作品の制作を通じて、新しい市場を開拓しつつあります。また、環境意識の高まりにより、再生素材を使用するという琉球ガラスの本質が再評価される動きも出てきています。持続可能性をキーワードに、国内外の消費者に対して新たなアピールが可能です。実際canosaが販売している「琉球ガラス」は泡盛の瓶を回収して原料にしている「再生ガラス」です。しかし作家さんは、泡盛の需要の縮小、瓶から紙パックへの移行などの理由で、泡盛の瓶を集めるのもご苦労されています。
そんな中でうるま市にある「再生ガラス工房てとてと」の作家さん、松本 栄(まつもと さかえ)さんは、2021年に沖縄の海岸に大量に漂着した軽石を琉球ガラスの原料として活用する取り組みを始めました。2021年10月、小笠原諸島の海底火山「福徳岡ノ場」の噴火により発生した大量の軽石が沖縄の海岸に漂着し、漁業や観光業に大打撃を与えました。松本さんは、恩納村や読谷村の海岸で実際に軽石が砂浜を覆い尽くす光景を目の当たりにし、自然の脅威と美しさを感じたといいます。この経験が、軽石をガラスの原料として再利用する発想の原点となったそうです。 松本さんは、従来から泡盛の廃瓶を再利用して琉球ガラスを製作していましたが、軽石を新たな原料として取り入れるには、いくつかの課題がありました。軽石には塩分が含まれており、そのままではガラスの品質に影響を及ぼすため、塩抜きや天日干し、乾燥といった前処理が必要です。さらに、軽石を粉砕してガラスの原料とするには、専用の設備が求められました。これらの課題を克服するため、松本さんはクラウドファンディングを活用し、必要な機材を導入することで、軽石ガラスの製作を本格化させました。 松本さんの取り組みは、単なる素材の再利用にとどまらず、環境問題への対応や地域社会への貢献を目指しています。軽石ガラスの売上の一部は、軽石の影響を受けた漁業関係者や地域社会に還元されており、持続可能な社会の実現に寄与しています。また、軽石ガラスは、自然災害による被害を価値あるものに変える「天災を天財に」という理念のもと、SDGsにも貢献しています。松本さんは、今後も軽石を活用した琉球ガラスの制作を通じて、環境保護や地域振興に取り組むとともに、伝統工芸の新たな可能性を追求していくそうです。canosaも松本さんの制作した「軽石の琉球ガラス」を、工房に伺った際に何度も拝見しています。松本さんの軽石の作品は、深いグリーンに沈む細かい気泡がまるで「沖縄の海に深く潜った時の風景」に似て、それは美しいものでした。
琉球ガラス、それは全てが失われた沖縄の再生の歴史と将来を映し出す鏡なのかも知れません。
琉球ガラスの商品ページはこちら ⇒ 再生ガラス工房てとてと