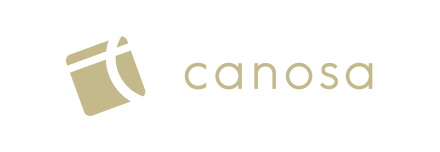canosa story Vol. 22 沖縄で学び、益子で育った - 益子と沖縄の深い絆
【canosa story Vol. 22】 第22回目
今回は益子と沖縄の焼き物について(吉良のレポート)
羽田空港から車で北へ向かうこと約二時間半。北関東自動車道を真岡で降り、益子町に入る頃には、車窓に広がる風景が次第にやさしく、どこか懐かしさを帯びてくる。道沿いには、素朴ながら洗練された佇まいの陶器店やギャラリーが点在し、町の静けさの中に確かな創造の気配が漂っている。焼き物市を来月に控えた平日の昼下がり、春の陽光に照らされた町並みは、どこか控えめな華やかさを湛えながら、訪れる者を柔らかく迎え入れてくれるようだった。
関東に長く住んでいながら、この地を訪れたのは不思議にも今回が初めてだった。若い頃から横川の「峠の釜めし」(釜が益子焼)には馴染みがあり、東日本の代表的な焼き物の町「益子」は身近だった。だが、沖縄から見ると遠い存在だった。宿泊施設も少なく、観光地としての賑わいよりも、地道なものづくりの空気が色濃く漂うこの町に、旅人がふらりと立ち寄るのは簡単ではない。
しかし、この“沖縄から遠い益子”こそ、実は焼き物という土の芸術を通じて、沖縄と深く結びついている。その静かな絆の中心には、二人の偉大な陶芸家の存在がある。人間国宝である濱田庄司と金城次郎──ひとりは益子焼の中興の祖として栃木の地に腰を据え、もうひとりは沖縄・那覇の壺屋に根を張った陶工である。
濱田庄司が益子に窯を構える以前、彼は「民藝」という理念のもと、日本各地を旅していた。柳宗悦、バーナード・リーチらとともに、日常に寄り添い、使われることで完成する「暮らしの美」を求めて、さまざまな地方の工芸を訪ね歩いた。その旅の中で、彼の心を強く打ったのが、沖縄・那覇の壺屋焼だった。
沖縄の土でつくられた器は、どこか陽気で大らかで、自由な筆遣いが生きていた。特別に飾らない素朴さの中に、確かな美と技があり、同時に生活に密着した実用性があった。それはまさに、濱田が求めていた「民藝の理想」そのものであり、焼き物という表現において「自然であること」がいかに美しいかを教えてくれた出会いでもあった。
その壺屋で濱田が出会ったのが、金城次郎である。1912年、壺屋の陶工の家に生まれた金城は、少年の頃から父に師事し、地元に根差した焼き物の技術と精神を受け継いだ。戦後の混乱期に濱田が再び沖縄を訪れた際、ふたりは本格的に出会い、互いの作品と人柄に惹かれ合っていく。濱田は金城の器に、荒削りながらも力強く、どこか祈りにも似た美を感じ取った。そして金城は、濱田のまっすぐな眼差しと言葉に励まされ、自らの表現に確信を深めていった。
彼らの関係は、単なる師と弟子ではなかった。濱田と金城は、時代も文化も違う場所に生きながら、「美は生活の中にある」「手の技こそが真実を語る」という民藝の精神を深く共有する同志だった。濱田が沖縄で感じた「自由で自然な焼き物の魂」は、金城の仕事の中に確かに宿っていた。
やがて濱田は、金城の作品を本土に紹介しはじめる。東京・駒場の日本民藝館や益子参考館をはじめとする場で、金城の壺や皿は人々の注目を集め、そこに込められた沖縄の光と風、そして土の匂いに、見る者は心を奪われた。柳宗悦はその力強くも温かい作風に深い敬意を抱き、バーナード・リーチは「沖縄の生命そのものが器に宿っている」と語った。
それでも金城自身は、自分の作品を芸術とは呼ばなかった。「わんはただの、やちむんぬぬーさ(焼き物の人)だよ」と静かに語った彼の言葉には、民藝の根底にある“使う人のために作る”という誠実な哲学が込められている。
1950年代以降、金城次郎の名は全国に知られるようになり、1972年には沖縄出身として初めて人間国宝の認定を受ける。この報に接した濱田庄司は、「自分が選ばれたときよりも嬉しい」と語ったという。そこには、互いの歩みを支え合いながら、時代を超えて通じ合った心と心の、深く静かな絆が感じられる。
そしてその絆は、今も形を変えながら受け継がれている。
たとえば、沖縄・竹富島に窯を構える五香屋の森田氏は、益子で修業を積んだ陶芸家のひとりである。沖縄の風土と民藝精神に根ざした作品を生み出しながら、濱田が育てた益子の土の記憶をその手に刻んでいる。また、島根の出西窯で研鑽を重ねた後、現在は益子の星の宮製陶所で作陶する高橋あいさんも、沖縄や民藝に強く魅かれる若き陶芸家である。土地を越え、思想を継ぐその姿勢は、まさに濱田と金城が交わした眼差しの延長線上にある。
一流の陶芸家は一流のコレクターであることが多い。現在、益子にある「濱田庄司記念益子参考館」では、濱田の旧宅や工房を中心に、彼の作品や、沖縄の影響が色濃く残る陶器が展示されている。飴釉の皿や、力強くもどこか柔らかな線が踊る壺の数々からは、彼が沖縄の土と対話した時間が静かに滲み出ているようだ。
濱田はかつて、自らの道のりをこう語った。「京都で道を見つけ、イギリスで確信し、沖縄で学び、益子で育った」。その言葉には、単なる場所の遍歴以上に、人生の中で出会い、学び、根を張った文化と人々への深い敬意が込められている。
益子と沖縄。 一見遠く離れた土地同士は、陶工たちの手を通じて確かに結ばれていた。その絆は今も、益子の静かな町並みの中で、焼き物に宿る「心」として、脈々と息づいている。
益子焼の商品ページはこちら ⇒ 星の宮製陶