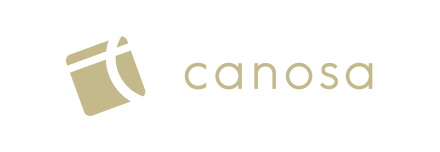canosa story Vol. 23 こぎん刺しと林檎
【canosa story Vol. 23】 第23回目
今回は青森県のこぎん刺しのストーリーです。(吉良のレポート)
お盆が過ぎ、ねぷた祭りの熱気も落ち着いた夏の終わりに、青森県弘前市を訪れた。車で大鰐町を抜け前方に緑拡がる平野が望めると、その向こうに穏やかにそびえる岩木山の姿が圧倒的だった。山裾には雲がかかり、その稜線は力強く弘前の街を包み込んでいるように見えた。
弘前市内は観光のピークを過ぎていて、落ち着いた雰囲気が漂っていた。歩道の脇には、ねぷた祭りの名残をとどめる飾りがところどころに残っていて、つい先日まで街を包んでいた賑わいが想像できた。日差しはまだ強いが、朝晩にはほのかに秋の気配が混じり始めていた。
市内から少し離れて岩木山の麓を走ると、そこには夏から秋へと移りゆく美しい景色が一面に広がっていた。緑の葉の奥には、少しずつ赤みを帯び始めた実がぶら下がっている。木によってはすでに実がずっしりと大きく育ち、色づきの違いから季節の進み具合を目で感じることができた。農家の方たちは収穫に向けた準備を始めていて、実の状態を確かめながら、一つひとつ丁寧に手をかけていた。その姿は、ただ農作業というより、何かを育て見守るような静かな誇りと収穫間近の安堵感が感じられた。
今回弘前を訪れたのは、「弘前こぎん刺し研究所」で、canosaで扱うための新しい「こぎん刺し」の作品を選ばせていただくためだった。市内中心部にほど近いながら、静かな住宅街にあるこの研究所は、昭和30年に設立され、かつて農村で着られていた麻布の作業着に刺されていた「こぎん刺し」を保存・研究・発信する場として活動を続けている。
こぎん刺しは、悲しい歴史の中で生まれた苦肉の策が偶然に生み出した青森県を代表する工芸品だ。江戸時代、津軽藩が「農民倹約分限令」を出したことで、木綿を着ることが許されなかった農民たちが、麻布の衣服を補強し、暖かくするために始めた技法が起源と言われている。白い木綿糸で細かく刺された幾何学模様には、布を強くするという機能性に加え、美意識や暮らしの中の知恵が込められている。木綿だけでなく色物なども禁じられたことが、図らずもこぎん刺しの美しい紺と白のコントラストを守ることに繋がった。 その後、さまざまな模様が生まれたが、代表的な菱形に刺すようになったのは江戸時代後期のことらしい。館内を案内して頂いたが、展示室には時代ごとの刺し模様が丁寧に保管されており、一つ一つの模様が、当時の生活のリズムや季節の移ろいを思わせた。
とくに印象に残ったのは、林檎の花や実をモチーフにした現代の作品だった。こぎん刺しが自然や季節の風景と深くつながっていること、そして今も新しいかたちで生き続けていることがよく伝わってきた。
弘前こぎん刺し研究所には80人ほどの職人さんが登録されていて、その殆どは主婦など女性であるそうだ。職人さんには、大物を刺す人、小物が得意な人など、それぞれの技術や生活スタイルに合わせて製作を分担している。現在は衣服よりもポーチやバッグなどの小物を製作することが多く、それらの制作には下書きを用いず、「何番目の縫い目から何目刺す」といった指示書と仕上がり図をもとに進められる。基本的に刺すのは「奇数の縫い目」と決まっているとのことだ。
弘前こぎん刺し研究所も創立80周年を機に世代交代を進めて、さらなる社業発展を目指している。同研究所は1942年、「弘前ホームスパン」の名で木村産業研究所内に設立され、1962年に社名を弘前こぎん刺し研究所に変更した。こぎんの資料収集などに取り組む一方、海外への普及や有名百貨店などとのコラボ商品の開発などを積極的に行い、こぎん文化・産業の発展に尽力してきた。一昨年(当時)、4代目の代表取締役・所長として新たな研究所の顔となった千葉弘美さんは、「プレッシャーと不安はあるが、今までのことを守りながらも新しいことにチャレンジしていければいい」と抱負を語っている。
こぎん刺しも林檎も、すぐに完成するものではない。ひと針ずつ、ひと季節ずつ、時間と手をかけて形にしていく。その「手間を惜しまない」精神が、弘前という土地には根づいているように思った。
帰り道、午後の光の中で岩木山の麓を走った。山は少しだけ色を変え、空の青と溶け合っていた。その姿に、林檎の実りとこぎんの刺し模様が重なって見えた気がした。
こぎん刺しの商品ページはこちら ⇒ 弘前こぎん研究所