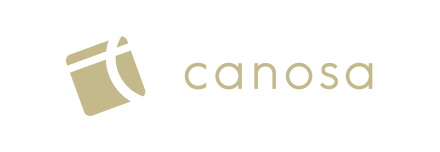canosa story Vol. 25 苦難を乗り越え、未来へ繋ぐ陶器の灯り – 小石原焼マルワ窯
【canosa story Vol. 25】 第25回目
今回は福岡県の小石原焼きについてのお話です。(吉良のレポート)
福岡県の東峰村で約350年にわたり受け継がれてきた小石原焼(こいしわらやき)は、その素朴で温かみのある風合いが特徴の陶器です。生活に寄り添う「用の美」を追求し、日本で初めて国の伝統的工芸品に指定されたことでも知られています。
小石原焼の魅力は、飛び鉋や刷毛目、櫛目といった独特の技法によって生まれる幾何学的な文様と、土の温もりを感じさせる質感にあります。これらはすべて職人の手仕事によって生み出され、一つとして同じものはありません。
この小石原焼は、山を隔てた大分県日田市で焼かれる小鹿田焼(おんたやき)と深い関係があります。1705年に小石原焼の陶工が招かれて小鹿田焼が開窯したことから、この二つは「兄弟窯」として知られています。
共通の技法が多く見られる一方で、二つの窯は異なる道を歩んできました。小鹿田焼が「一子相伝」の形で昔ながらの製法を頑なに守り続けてきたのに対し、小石原焼は時代に合わせて柔軟に発展し、目を瞠るような現代的な作風も多く生み出されてきました。それぞれの窯元を訪れることで、兄弟窯がたどってきた歴史の違いを感じることができます。
小石原焼の窯元の一つであるマルワ窯は、伝統的な技法を守りながらも、現代のライフスタイルに合わせた新しい表現に挑戦し続けています。現在の窯主である太田富隆(おおた とみたか)さんは、ガーデンテーブルなどの大物も手掛け、日本伝統工芸展や西日本陶芸美術展などで数々の受賞歴を持つ実力者です。
しかし、マルワ窯は2023年7月6日に大きな試練を経験しました。隣接するカフェから発生した火災により、工房は甚大な被害を受けます。長年築き上げてきた窯や機械設備だけでなく、陶器の命ともいえる釉薬やその調合データや材料、そして過去の作品の数々まで、ほとんど全てが焼失してしまいました。
深い悲しみの中、太田さんは再建への強い決意を胸に立ち上がりました。全国からの温かい支援やボランティアの協力、そして地域の人々の支えを受け、不屈の精神で復興への道を歩み始めました。この困難な経験は、太田さんのものづくりへの情熱をさらに強くし、器に込める思いをより一層深めています。
そして、マルワ窯には心強い後継者たちがいます。火災という苦難を家族で乗り越え、父から子へと受け継がれる小石原焼の技術と精神は、マルワ窯の新たな歴史を築いています。彼らの手によって生み出される器には、不屈の精神と、使う人々への深い感謝、そして未来への希望が込められています。
マルワ窯の器は、食卓に温かい雰囲気をもたらし、料理を引き立てるだけでなく、使うたびに手になじみ、愛着が湧くような魅力を持っています。伝統的な文様を用いた落ち着いたデザインから、現代的な食卓にも馴染むモダンなものまで、幅広い品揃えが特徴です。
canosaが2回目に訪れた時は、標高の高い東峰村に近づくにつれ、前週までの大雪の名残で景色は白く覆われ、村を静寂が支配していました。しかし東峰村には、約50軒もの窯元が集まっており、毎年5月と10月には「民陶むら祭」が開催され、多くの陶器ファンで賑わいます。マルワ窯の飯釜で炊いた白米も大人気で、その美味しさに皆驚くそうです。
各窯元を巡り、それぞれの個性を感じながらお気に入りの器を見つけるのも小石原焼の楽しみ方の一つです。
小石原焼とマルワ窯の器は、日々の食卓を豊かに彩り、使うたびに温かい気持ちにさせてくれるでしょう。ぜひ、実際に手に取って、その魅力を感じてみてください。
マルワ窯の作品はこちら→ マルワ窯