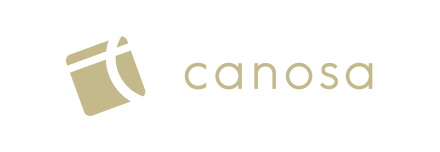canosa story Vol. 26 北海道八雲町の木彫り熊の歴史と今
【canosa story Vol. 26】 第26回目
今回は北海道の木彫り熊のお話です。(吉良のレポート)
冬は寒さが厳しい北海道。その南部に位置する八雲町は、日本で初めて木彫りの熊が誕生した地として知られています。八雲の木彫り熊は、単なるお土産品ではありません。そこには、大自然の中で生きる人々の暮らしと、熊という存在への複雑な思いが宿っています。
近年、都市部や住宅地での熊の出没がニュースになるたび、その恐ろしさが強調されます。しかし、八雲の職人たちが彫り上げる熊は、人間と野生動物が共生してきた歴史の証であり、自然への畏敬の念が込められた存在なのです。
八雲町に木彫り熊が誕生したのは、大正時代にまで遡ります。尾張徳川家第19代当主 徳川義親(よしちか)公爵がスイスから持ち帰った木彫りの熊を参考に、農閑期の収入源として農民たちが彫り始めたことがきっかけでした。しかし、彼らが創り出した熊は、スイスの装飾的な熊とは全く違う独自の進化を遂げます。
かつて、日本の多くの家庭には、テレビの上や玄関に鎮座する、鮭をくわえた木彫り熊がありました。北海道土産の定番として、誰もが一度は目にしたことがあるでしょう。無骨ながらも愛嬌のある表情、そしてくわえられた鮭の力強い姿は、北の大地の象徴として、私たちに温かい思い出をもたらしてくれました。
長い歴史を持つ八雲の木彫り熊ですが、現代においてもその文化は進化を続けています。伝統と革新をつなぐ重要な存在が、加藤貞夫(かとう さだお) 氏です。自らを「熊大工」と称し、温かみのある作品を数多く残しました。指物師として培った繊細な技術を活かし、より細かく繊細な毛彫りを施す独自のスタイルを確立しました。また、愛らしいフォルムで知られる柴崎重行(しばさき しげゆき) を尊敬し、彼のようなデフォルメされた作風にも挑戦するなど、生涯を通じて探求を続けました。彼の作品は、2010年の上海万博にも展示され、国際的な注目を集めました。
また、SNSなどを通じて木彫り熊の魅力が再発見され、新たなファンを獲得しています。作家自身が制作過程を発信したり、オンラインで作品を販売したりすることで、北海道を訪れることが難しい人々にも、その魅力を届けています。このような新しい動きが、伝統工芸としての木彫り熊に新たな命を吹き込んでいます。
canosa でも個性的な熊の木彫りを取り揃えています。そのどれもが「熊」というより愛らしい「くま」。恵山の近くで制作する「YOUSUN」の作品は、「1日の始まりが楽しくなる」朝に使うコーヒーメジャースプーンやマドラーなど、使うのがウキウキするようなご機嫌なアイテムばかり。くまだけでなく、工房の周りの自然にインスパイアされた素敵なデザインの作品は、木材も道南の間伐材を使っており、canosaでも人気アイテムです。
また前述の加藤貞夫氏の作品に影響されて岐阜県で製作する「ギザグマ」さんの作品は、可愛く擬人化された動きのある楽しいくまばかり。こちらも早くもcanosaの人気アイテムになっています。
これらの木彫りくまは、現代のライフスタイルにも自然に溶け込み、使うたびに温かい気持ちにさせてくれるでしょう。ぜひ、機会があれば手にとって、そのずっしりとした重みと、丁寧に彫られた表情の中に、北海道の壮大な自然と、人々の温かい心が感じられるはずです。
また、北海道に行かれた際は、八雲町木彫り熊資料館にも立ち寄られることをお勧めします。