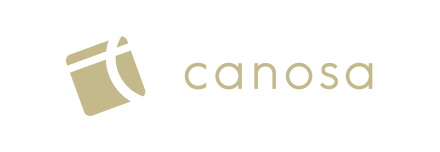canosa story Vol. 27 山葡萄のかごバックを持つということ
【canosa story Vol. 27】 第27回目
今回は山葡萄のかごバッグについてのお話です。(吉良のレポート)
山葡萄のかごバックを持つということ
北アルプスの麓にある森の奥深く、山葡萄の蔓が巨木に縋るように絡み合っています。山葡萄の蔓は、一年中採取できるわけではありません。職人は毎年、梅雨の時期にしか収穫できないと教えてくれました。雨に潤い、柔らかさを帯びたこの時期の蔓は、籠の素材となる籤(ひご)の加工に適したしなやかさと丈夫さを備えています。しかし、近年では熊の影が濃くなり、森に入るたびに緊張を強いられます。作家は細心の注意を払いながら、熊の活動時間と重なる早朝や日没前のわずかな時間に森に分け入るのです。
山葡萄の蔓を巡る状況は深刻です。近年、良質な蔓を確保できる場所は減少し、自然環境の変化も重なって、昔のように簡単には手に入りません。太い蔓は籠の骨格となるため、折れやすさや曲げ方に気を配る必要があります。一方、細い蔓は柔らかく編みやすい反面、乾燥や湿度で縮みやすく、均一に編むには熟練の感覚が不可欠です。
山葡萄のかごバッグは、一本の蔓から始まる長い旅を経て完成します。その手間と時間は、森の恵みと職人の技術が結びついた結晶です。
蔓の採取(6月〜7月)
梅雨の時期、職人は早朝または日没前のわずかな時間を選んで、熊の生息域でもある森へ分け入ります。籠に最適な蔓は、太さや節の間隔、そして何よりもそのしなやかさで選び抜かれます。採取できる期間は限られており、質の良い蔓を見つけるのは容易ではありません。山葡萄の蔓を早朝や夕方に収穫する理由は、蔓が柔らかくしなやかになるからです。採取された蔓は、丁寧に束ねられ、工房へと持ち帰られます。
蔓の下処理と皮剥ぎ(7月〜8月)
持ち帰った蔓は、その日のうちに下処理が始まります。まずは表面についた汚れや苔をブラシで丁寧に落とします。その後、特殊なナイフを使って蔓の表皮だけを慎重に剥いでいきます。この工程で、硬い木質部だけを残し、籤の素材となるしなやかな樹皮を取り出します。
天日干しと乾燥(7月〜9月)
剥いだ樹皮は、日陰でじっくりと乾燥させます。強い直射日光を避けるため、風通しの良い場所で数ヶ月かけて自然乾燥させます。乾燥が不十分だとカビが生え、乾燥させすぎると籤が折れやすくなるため、毎日状態を確認し、適切な湿度を保つ必要があります。この工程で、蔓は強くしなやかな素材へと変わります。
籤作り(9月〜10月)
乾燥させた蔓の樹皮を、かごの部位ごとに適した幅と厚さに籤と呼ばれる細いテープ状に整えます。太い蔓はかごの土台となる骨格用、細い蔓は繊細な編み込み用として、職人の手によって一本一本丁寧に手割りで加工されます。この作業は蔓の繊維質を壊さないよう、高い技術と集中力を要します。この段階で、既に数ヶ月の時間を費やしているのです。
編み込み(10月〜)
籤が完成したら、いよいよ編み込みに入ります。編み始める前に籤を水に浸して柔らかくし、編みやすい状態にします。太い籤でかごの骨格を組み、その間を細い籤で密に編み上げていきます。編み目の強弱、籤の重ね方、持ち手の美しいカーブなど、すべてが職人の経験と感覚に委ねられています。一つのバッグを完成させるのに、数十時間から数百時間かかることも珍しくありません。
仕上げ
編み上がったかごは形を整え、表面を丁寧に磨き上げます。職人の手で何度もなでられることで、山葡萄独特の光沢と深みが増し、使い込むほどに手に馴染む風合いが生まれます。
canosaで扱う山葡萄のかごバッグは、収穫から完成までを北アルプス山麓に住むひとりの作家が一貫して手がけています。この一貫作業には、単に効率を追求するのではなく、蔓の性質や森の状況、季節ごとの湿度や温度までを肌で感じ、一つひとつの籠に魂を込められるため、分業制よりも美しい仕上がりになりやすいのです。太い籤と細い籤の相性、編み目の強弱、持ち手の美しい曲線。それらすべてに職人の経験が反映され、使うほどに手に馴染む一生もののバッグが生まれます。実際、山葡萄の籠は150年以上の耐久性があるといわれています。代々受け継ぐこともできる、まさに時間と手間の結晶なのです。
百貨店で数十万円で販売される理由もここにあります。蔓の収穫方法、熊や自然のリスク、蔓の下ごしらえの労力、そして一人の作家が全てを一貫して仕上げる手仕事。それらの手間と時間がすべて価格に反映されているからです。
canosaでは太籤と細籤をほぼ同価格にしています。一般には細籤の方が製作に手間がかかるため高価です。細い蔓を均一な幅に揃え、緻密に編み上げるには、熟練した技術と膨大な時間が必要です。特に、5mm以下の極細の籤は、しなやかで柔らかい分、加工が難しくなります。太籤の製作は蔓の幅が広いため、編み上げるのにかかる時間は短いですが、太く長い蔓を探し出して収穫する手間がかかります。籤を整え編み上げる手間、太く長い蔓を見つける手間。どちらが簡単でどちらが大変だと簡単には比較できません。このような理由から、価格差がないのです。
昨今深刻化する環境変化により、良質な山葡萄の蔓はますます希少になっています。資源は無限ではないのです。だからこそ、この北アルプスの森から生まれる籠を手にすることは、自然と職人の時間を共有することでもあります。持ち手に触れ、編み目の感触を確かめながら、森の空気と職人の息遣いを感じてください。
多くの人が山葡萄のかごバッグに憧れを抱いていると思います。前述の手間や技術を考え、輸入品などと比較すると、決して「お高い!」とは感じられないはずです。むしろ150年使えることを考えれば、大変お得ではないでしょうか。
山葡萄のかごバッグはただの道具ではなく、自然と職人、あなたやあなたの子孫の暮らしをつなぐ物語そのものなのです。そして使い込む時間が艶となり、あなたの時代を次世代に受け継ぐ、自然から生まれた資産なのです。
山葡萄やあけびのかごバックはこちら→ canosa collections