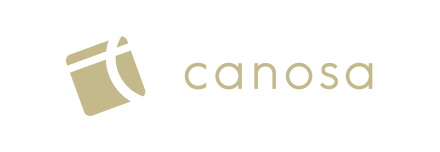canosa story Vol. 28 浜比嘉島の草木染めと機織り
【canosa story Vol. 28】 第28回目
今回は沖縄の浜比嘉島で草木染めと機織りをしている作家さんについてのお話です。(吉良のレポート)
沖縄の離島、浜比嘉島。深い緑と透き通る海に囲まれたその景色は、いつでも訪れる人々の心にしみわたります。島全体を包む静寂の中、神話が息づく神秘的な空気を感じられます。しかし離島とは言うものの、沖縄本島から海中道路や浜比嘉大橋を経由して車で簡単にアクセスできることも魅力の一つです。
そんな浜比嘉島に、静かに佇む草木染めと機織りの工房「樹庵」。ここでは、「島の自然を染め、情景を織り込む」をテーマに、島の恵みを丁寧に染め上げた糸を使い、静かに機を織る一人の女性がいます。渡辺智子さんが織りなす布は、沖縄の自然や風土を映し出し、穏やかな温もりに満ちています。その作品は、自然と調和し、時の流れを忘れるような深い安らぎを与えてくれる、素敵なアイテムばかりです。
染めに使われるのは、浜比嘉島の井戸水です。この水が、一つひとつの作品に、島のミネラルと独自の風合いをもたらします。「樹庵」の手によって、島のあちこちで見かける車輪梅(シャリンバイ)からは深みのある茶色が、長寿の木として知られるフクギからは温かみのある黄色が生まれます。また、生命力あふれる相思樹(ソウシジュ)からは赤褐色、そして古くから染料として使われてきたホルトノキからは穏やかな灰緑色が紡ぎ出されます。これらの色は自然や人間とうまく調和し、決して目立つことはありませんが、織る人の感覚や想いを映し出します。中でも、深い茶色に染めるため染めと乾燥を数十回も繰り返す車輪梅や相思樹染めは、「樹庵」の作品を象徴する色であり、渡辺さんの沖縄の自然への深い敬意と手間暇を惜しまない手仕事の結晶です。
島の草木が彼女によって染められた糸や布を目にするとき、その奥に、これらを染料とすることを見出した名もない人々の観察と知恵が眠っていることに感動を覚えます。染色とは、ただ色を移す作業ではなく、色がどこから来たのかを辿る旅でもあるのです。
これらの草木から抽出した染料で丁寧に染められた糸は、渡辺さんの手で機で織られ、一枚の布へと姿を変えます。自然の色と手仕事の温もりが重なり合って生まれる「樹庵」の作品は、島の穏やかな時の流れを写し取り、改めて持つ人に深い安らぎと喜びを与えてくれます。
「樹庵」の草木染めのストールを手に取れば、やわらかな肌触りとともに、シャリンバイの茶色からは海風に耐える島の木の強さが、フクギの黄色からは降り注ぐ太陽の光が感じられるでしょう。作品は単なる日用品ではありません。それは、島の自然と手仕事の温もり、そして悠久の物語をつなぐ天工造化なのです。一つひとつ異なる表情を持つ作品は、身につける人の日常に、自然の息吹と静かな感動をもたらしてくれます。
「樹庵」を訪れる人々は、織り機が奏でる軽やかな音を聞きながら、渡辺さんが紡ぎ出す物語に耳を傾けます。そこには、大量生産される現代の品々とは違う、作り手と自然、そして作品が一体となった特別な時間が流れています。自然の恵みに感謝し、丁寧に作られた作品は、私たちに「本当の豊かさ」とは何かを静かに問いかけるのです。
今日も機(はた)を織るたびに、カタカタと心地よい音が島に響きます。その音は、まるで浜比嘉の海に寄せては返す波の音に重なるかのようです。機を動かす手の動きも、寄せては返す波の動きそのもの。それは、千年も前から変わらない島の風景と、千年も前から受け継がれてきた手仕事が、静かに共鳴し、新たな作品を生み出している瞬間なのです。
「染と織 樹庵」の商品はこちら → 染と織 樹庵