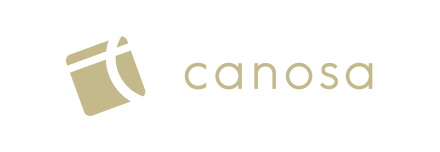canosa story Vol. 29 沖縄の聖地巡礼、東御廻りとマース袋
沖縄では古来より、祖先信仰や自然信仰に根ざした精神文化があり、太陽の昇る東の海の先に理想郷ニライカナイがあると考えられていました。東御廻りとは、琉球王国時代、国家の繁栄と五穀豊穣を祈願して行われた祭祀で、ニライカナイから渡来した沖縄の創世神・アマミキヨにゆかりのある14か所の聖地を巡る神聖な旅です。
【14か所の聖地】
① 園比屋武御嶽(そのひゃんうたき)
沖縄県那覇市首里真和志町1丁目17−3(首里城内)
② 御殿山(うどぅんやま)
沖縄県島尻郡与那原町与那原658(御殿山青少年広場内)
③ 与那原親川(よなばるうぇーがー)
沖縄県島尻郡与那原町与那原556(親川広場内)
④ 場天御嶽(ばてんうたき)
沖縄県南城市佐敷新里153
⑤ 佐敷上グスク(さしきがみぐすく)
沖縄県南城市佐敷116
⑥ テダ御川(てだうっかー)
沖縄県南城市知念知名(知名崎の駐車場から徒歩)
⑦ 斎場御嶽(せーふぁうたき)
沖縄県南城市知念安座真865(入場料支払い)
⑧ 知念グスク(ちねんぐすく)
沖縄県南城市知念知念 上田原
⑨ 知念大川(ちねんうっかー)
沖縄県南城市知念1072
⑩ 受水走水(うきんじゅはいんじゅ)
沖縄県南城市玉城百名1681
⑪ ヤハラヅカサ
沖縄県南城市玉城百名(波打ち際)
⑫ 浜川御嶽(はまがーうたき)
沖縄県南城市玉城百名707
⑬ ミントン城跡(みんとんぐすく)
沖縄県南城市玉城仲村渠705(民家内/必ず声を掛け入場料支払い)
⑭ 玉城グスク(たまぐすくぐすく)
沖縄県南城市玉城門原444(階段使用禁止/左側の石畳から登る)
首里城内の園比屋武御嶽から始まり、太陽が昇る東方(あがりかた)、または東四間切(あがりゆまじり)といわれる、太陽神信仰と深く結びついた、与那原・佐敷・知念・玉城などの地域に点在する聖地を廻る巡礼になります。
これらの場所は、それぞれ独自の歴史と神秘を保ち、琉球の文化を現代に伝えています。この巡礼は、ただの観光ではなく、沖縄の歴史と文化への深い理解、自然と祖先への尊敬を育む神聖な行事です。近年では、心とからだを癒やす“自己発見の道しるべ”として、あるいは“健康的なレクリエーション”として「東御廻り」を行う人も増えています。しかし、どの聖地も沖縄の人々にとって神聖な祈りの場所であることを忘れてはなりません。
【東御廻りの心得】
・礼をし、挨拶をしましょう。
自分の名を名乗り、「見学に来ました」と唱えましょう。
・敬う心で挑み、身体を清める。
聖地は祈りの場所であることを念頭に。入浴するなど、身を清めることがエチケットです。
・聖地内にあるものを持ち出さない。
石や植物などを記念に持ち帰るのは控えましょう。
・祈りをさえぎらない。
拝みをしている最中の人に声をかけてはいけません。大声で騒いだり、むやみに歩き回ったり、動画などを撮るのも控えましょう。
・ガイドがいるところでは、その案内に従いましょう。
独特の価値観や文化を知るためにも、解説に耳を傾けてください。(斎場御嶽など)
・香炉や積み石を踏まない。
香炉は神聖なものです。誤って足で踏みつけないよう十分注意しましょう。
・ゴミを出さない、汚さない。
御嶽を美しく保つように心がけましょう。自分のゴミは必ず持ち帰るのは当然ですが、もし他のゴミを見かけたら回収するくらいの気持ちで巡りましょう。
・不法駐車をしない、民家に立ち入らない。
駐車場がない御嶽も多くあります。迷惑駐車や不法駐車は厳禁です。また、「ミントン城跡」は民家内にあります。必ず家主に声をかけ、車を止める場所の指示を仰ぎましょう。御嶽を維持するための入場料などがある場合は、必ず支払いましょう。
四国八十八か所やスペインのサンティアゴ巡礼と違い、東御廻りには御朱印帳の記帳やスタンプはありません。東御廻りは自分の内なる部分の記憶に留め、祖先を敬い、自然の恵みに感謝しましょう。
また、各聖地には案内板が整備され、車で土地勘があれば1日で巡ることも可能です。しかし、東御廻りにはしきたりや作法があり、その通りに行うと1日では廻りきれません。付近の住民の生活に迷惑をかけないよう、十分な余裕を持って巡りましょう。
ところで、canosaの定番商品として人気のある「機織工房しよん」の「マース袋」には、作家さん自身が東御廻りを行い、お清めしたマース(お塩)を大切に包んでいます。
御嶽やグスクは見晴らしのよい高台にあることが多いため、階段や石畳を上るだけで体力が消耗します。そんな苦労を凝縮したマースが手織りの袋に入っているのです。単なるアクセサリーやキーホルダーではありません。大切な人へのお土産や、自分自身のお守りとして、沖縄と持つ人へのうむい(思い)を持ち帰ってみてはいかがでしょうか。もちろん、canosaの“うむい(思い)”も込められたお守りなのです。
マース袋はこちら → 東御廻りのマース袋