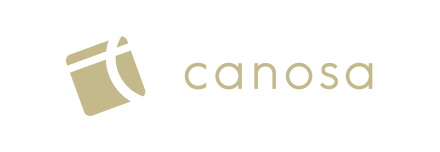canosa story Vol. 31 静かな里で生まれる熱いうつわ - 宮崎・生楽陶苑のスリップウェア
九州には、焼き物の名産地として知られる地域がいくつもあります。福岡の小石原焼、大分の小鹿田焼、佐賀の有田焼、長崎の波佐見焼、熊本の小代焼、鹿児島の薩摩焼など、その名を挙げればきりがありません。
では宮崎はどうでしょうか。本庄焼、小松原焼、小鹿焼といった窯はあるものの、他県の大きな産地のように全国的な知名度があるわけではありません。その流れを静かに受け継ぐ“知る人ぞ知る”窯元が点在する、といった佇まいです。
安土桃山時代から江戸時代にかけて、茶道の隆盛とともに焼き物文化は大きく発展しました。当時の各藩にとって陶磁器は財政を支え、藩の威信を示す重要な産業。九州の薩摩藩や肥後・肥前の諸藩は専売制のもとで生産と流通を管理し、現金収入の確保や輸出による外貨獲得、地元資源の活用といった恩恵を受けていました。
一方、宮崎県(当時の日向国)には大藩が置かれず、京・大坂・江戸といった大市場への物流も限られていました。徳川幕府の政策上、大規模に産業を育てる土台が整いにくかったという背景があります。
そうした歴史を経た今の宮崎には、静けさの中に強い熱を宿して作陶する人たちがいます。
宮崎県三股町──鹿児島県境に近く、遠く霧島連山を望む豊かな緑の中で、「生楽陶苑」の二代目・園田空也さんが静かに土と向き合っています。彼の手から生まれるスリップウェアは、一目でそれと分かる独特の表情をまとっています。その背景には、東京で企業デザイナーとして働いていたという経歴がありました。
園田さんのご両親は三股町で「生楽陶苑」を開いた陶芸家ですが、園田さんは東京藝術大学を卒業後、しばらくはパソコンに向き合うデザイナーの仕事に従事していました。
転機が訪れたのは27歳のとき。ふと立ち寄った陶芸教室で、幼いころから染みついていた手仕事の感覚と、粘土に触れる楽しさが一気によみがえります。「これなら仕事にできる」と確信し、迷わず陶芸家の道へ。デジタルからアナログへと大きく舵を切った経験が、現在の作風の核となっているのかもしれません。
探求心はその後も尽きず、ヨーロッパ各地を巡ってスリップウェアの温かい装飾技法に魅了されます。釉薬の下に化粧土(スリップ)で模様を描くこの技法は、「和洋を問わず馴染む雰囲気」と「力強く素朴な表情」を求めていた園田さんに強く響きました。
帰国後は、三股の土地ならではの白砂(シラス)やワラ灰など自然の釉薬と組み合わせ、「生楽陶苑」独自のスリップウェアを築き上げています。
園田さんの器には、裏面を含めた細部への気配りが際立っています。「器は使ってこそ意味がある」という信念のもと、角を丸くして欠けにくくし、タタラ作り(板状の粘土を組み合わせる技法)で平らになった底面は丁寧に磨き上げ、テーブルを傷つけないようつるりと滑らかな仕上げにしています。
この“裏側の美学”には、デザイナー時代に培ったユーザー目線と、初代が大切にしてきた「生まれる楽しさ」への想いが息づいています。表面の華やかな模様だけでなく、洗って乾かす何気ない瞬間にも愛着が湧く──園田空也さんの器は、細部に宿る優しさと手仕事の力強さで、日々の食卓を静かに、そして確かに豊かに彩り続けています。
生楽陶苑の近くには、美しい渓谷・長田峡があります。切り立った巨岩や奇岩が続き、エメラルドグリーンの清流がきらめく名所で、川沿いには遊歩道が整備され、せせらぎを聞きながら散策を楽しめます。マイナスイオンを浴びられると人気で、特に秋の紅葉は宮崎県内でも有数の美しさです。
canosaが生楽陶苑を訪れたのは晩秋。三股町の空気も長田峡の渓谷も静けさの中に紅葉が鮮やかに映えていました。遊歩道には、三股町の陶芸家が製作したカッパのオブジェが14体設置され、土地の自然と陶芸が結びついた風景をつくっています。
そんな宮崎の陶芸の里・三股町で、園田空也さんは今日も静かに熱く炎を灯し続けています。