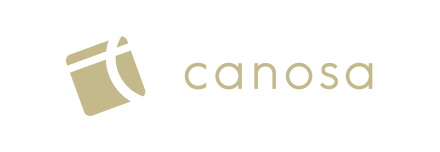canosa story Vol. 34 日田の皿山 小鹿田焼
「ゴットン、ゴットン」と唐臼(からうす)が心地よく響き渡る、静かで小さな集落。数日前の雪がまだ残る真冬の日、canosaは日田の皿山を訪れました。
柳宗悦氏がこの地を訪れ、そのあまりの純朴さに衝撃を受けて残した言葉は、今も民藝の精神そのもののように語り継がれています。柳氏は、近代化で機械化が進む工芸の世界において、奇跡的に残った小鹿田の体制をこう称えました。
「もし私に、日本に一軒だけどうしても残さねばならぬ仕事場を上げろと云われたら、私は日田の皿山を指したいと思う。」(柳宗悦『日田の皿山』より)
小鹿田焼の技は代々、弟子を取らず、外部の人間が職人になることは基本的にありません。そう、まさに一子相伝。これにより、三百年の時を経ても作風が揺らぐことなく守られているのです。また、作家名を器に入れることはなく、すべて「小鹿田焼」として世に出る、徹底した無名の美が貫かれています。
その工程は土作りから始まります。集落総出で近くの山から土を削り出し、トラックで里へと運び込みます。運び込まれた岩のような土の塊は、里のあちこちに据えられた「唐臼」へと託されます。川のせせらぎとともに水を湛え、その重みでゆっくりと天秤を揺らす唐臼は、鹿威しのように「ゴットン」と重厚な音を響かせながら、昼夜を問わず数週間かけて土を細かく打ち砕いていきます。
こうして粉砕された土は、次に「水簸(すいひ)」という工程を経て、水の中で何度も丁寧に不純物を取り除かれ、磨き上げられていきます。水槽の中で沈殿を繰り返し、上澄みのきめ細かな泥だけを掬い取ることで、あの滑らかな肌触りの素地が生まれるのです。水を含んだ泥は「おろ(乾燥場)」へと移され、太陽と風の力に委ねられ、じっくりと水分を抜いていきます。自然のペースに合わせて適度な硬さになった土を、最後は職人がその手足で一心に練り上げ、ようやく「蹴ろくろ」の上へと運ばれます。
電気もガスも使わず、太陽の恵みと水の力、そして人の忍耐が折り重なって生まれる土。その健やかな土の温もりが、小鹿田焼の器ひとつひとつに宿っています。
小鹿田焼を彩る代表的な技法もまた個性的です。
刷毛目 : 化粧土を塗りながら、刷毛で連続した躍動感のある模様をつける。
飛び鉋 : ろくろを回しながら、金属のヘラで表面を削り、点々と連なる独特の模様をつける。
指描き : 化粧土が乾かないうちに職人の指先だけで描く技法。指の腹が通った跡には、土の温もりがダイレクトに残ります。
打掛けと流し掛け : 青釉や飴釉を柄杓で勢いよく掛け、あえて釉薬を滴らせることで色彩のアクセントを添える。
伝統的なのに古くない。緻密だけれど大らかで使いやすい。語り尽くせないその魅力は、今も多くの民芸ファンを魅了してやみません。
canosaにも坂本浩二窯の今年初窯となる美しい作品が届いています。あまりの出来栄えに、販売しようか自分で使ってしまおうか、今も本気で迷っているところです(笑)。